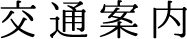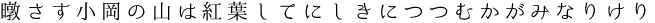
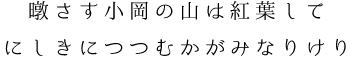
眼前に見上げんばかりの石段が出迎える。その石段、少し息切れしそうな七十段を登ると小島の山寺、久昌寺のこぢんまりとした伽藍が目の前に現れる。その境内から振り返れば、信濃川を一望しつつその奥には河岸段丘が広がる。津南の寺院の境内では一番の景観ではなかろうか。また、本堂欄間は熊谷(小林)源太郎作とも伝えられており、見所がある寺である。
さて、ここの七十五番の観音様は総代高橋家の持仏であったが享保年間の久昌寺本堂再建の際に安置されたと言われる。そしてその隣に四郎神様も一緒に安置されているが、こんな話が伝えられている。
「昔、盗賊が村を荒らしに来た時に村人達は金品を隠そうと山林へ逃げ込んだ。その時一人の母が過って四郎と言う名の子を背から滝へ落としてしまったと言う。それ以後、四郎の霊のさわりか村の子供に災難が続いた。そこで観音様の隣に四郎神様をお祀りすると災難は消えたという。」
そんな事から「子育観音」として信仰されてきたが、時と共に手を合わせる村人は減ってはきている。それでも七月十七日の例祭日には里芋の形を模した団子をお供えし供養を続けたいと今の住職は静かに言う。
因みに現在は自動車で境内まで行ける道が完備されていることも付け加えておこう。
(曹洞宗青年僧侶による「妻有百三十三番 霊場紀行」より)
同町内、大龍院三世笑外春哲和尚が開山した曹洞宗の寺院です。
久昌寺のはじまりは、天台宗「宝昌寺」として原村(現在:外丸集落の旧外丸小学校裏付近)
にあり、寛永十三(1636)年の地震の地滑りによって、現在地に移転しました。
現在の伽藍は、文化十一(1814)年、当寺九世 圓戒元明和尚によって建立され
ご本尊は釈迦如来坐像です。
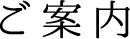
当寺には江戸時代の彫師・熊谷源太郎(本名:小林源太郎・武州玉井村〔現埼玉県熊谷市〕出身)
が、天保三(1832)年、三十三歳の時に描いた「双龍図」と嘉永五(1852)年五十三歳の時に竣工された
本堂の欄間7点が伝わっています。
「まくり」の存在と彫刻の技巧的観点から「まくり」、本堂の欄間7点、大間の欄間2点、向拝4点
木鼻6点が津南町の貴重な文化財として指定されました。
欄間は、一枚の木の板から掘り出された「龍」や「唐獅子と牡丹」「舜と象」など
中国の故事などを題材にした彫刻があります。
また「妻有百三十三番霊場」の七十五番目の霊場で「子育観世音菩薩」をお祀りしています。
(曹洞宗青年僧侶による「妻有百三十三番 霊場紀行」より)